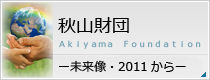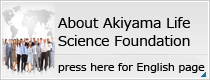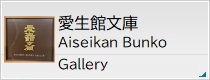⑴ 研究成果報告書
1.研究が終了次第、3ヶ月以内に「研究成果報告書」をご提出ください。遅れる場合は、その旨を財団事務局までご連絡ください。ただし、ジャーナル投稿、及び特許等の申請がある場合はそちらを優先し、受理後で結構です。
【作成要領】
① 「研究成果報告書」はワードファイルで作成頂き、書式は一般的なもので結構です。
ページ数の指定はございません。1ページ目には、助成研究テーマ名、受領者氏名、所属研究機関名、役職、共同研究者(奨励は不要)を日本語で記載してください。
② メール添付ファイルにてご提出願います。※紙媒体は不要です。
③ 会計報告の提出は必要ありません。
2.本研究の成果を学術雑誌等で発表される場合、公益財団法人 秋山記念生命科学振興財団(THE AKIYAMA LIFE SCIENCE FOUNDATION)の助成による謝辞(acknowledgements)のご記載をお願い致します。
3.学術雑誌等に掲載された場合には、当財団のHPにて公表致しますので事務局宛てに雑誌名とURLをお知らせ願います。(参考)
4.財団の助成金は、受領年度内に終了する研究を対象としています。
研究期間の延長が想定される場合は、その旨を財団事務局へ受領者ご本人より直接ご相談くださるようお願い致します。
⑵ アウトリーチ活動報告書
1.研究活動と並んで、アウトリーチ活動を実施して頂き、活動終了後3ヶ月以内に「アウトリーチ活動報告書」としてご提出ください。提出が遅れる場合は、その旨を財団事務局までご連絡ください。なお、アウトリーチ活動が多数ある場合は、まとめてご提出頂いても構いません。
【作成要領】
① 「アウトリーチ活動報告書」はワードファイルで作成頂き、書式は一般的なもので結構です。
ページ数の指定はございません。1ページ目には、アウトリーチ活動実施名、受領者氏名、所属研究機関名、役職を記載した上で、日本語で実施内容の報告をお願い致します。
② メール添付ファイルにてご提出願います。※紙媒体は不要です。
③ 会計報告の提出は必要ありません。
2.アウトリーチ活動に関してのレジュメ、チラシ等により事前の周知が可能です。また、報告書に活動の様子(写真)や感想をご記載頂けますと、当財団のHPにて公表致します。(参考)
秋山財団のアウトリーチ活動に対する基本的視点は、以下の4点です。
・特に小中学生・高校生・大学生などの若い世代に対する啓発を行う
・生命科学と地域社会との関わりについて問題提起を行う
・科学リテラシーの向上に取り組む
・秋山財団の考える生命科学はヒューマニズムに根差したものを希求する
【具体例】
<意見交換会・コラボ企画>
研究者が研究機関、分野等を越えた幅広いフィールドにおいて、意見交換・コラボ企画を実施する。
<出前授業>
小・中・高・大学等の教育機関や学校企画に講師として出掛けて行き、研究内容、研究に込める想い、 最新の話題等を説明する特別授業等を開催する。
<研究施設の公開>
市民や小・中・高校生等の若い世代に学内施設を公開・開放し、研究室で行われている最先端の研究の紹介と意見交流を行う。
<サイエンスイベント>
科学体験・実験、パネル展示等で、研究に関連する事例を分かりやすく紹介し、参加者と交流する。
<ワークショップ・シンポジウム>
市民を対象に研究の内容・成果を分かりやすく伝える工夫、科学リテラシーを高めるような啓発を行う。研究内容に関わる市民的関与の可能性を開示する。
<WEB>
研究室のHPやSNS等を通じて、広く一般市民や学生に向けて研究内容、目的、意義等を分かりやすく伝える。 また、一般市民や学生等とのネットワークを利用した双方向性を導入する。最先端の研究を分かりやすく紹介する為にマスメディア、プレスリリース、書籍等の活用もご検討ください。
※これまでの活動事例は、財団HP「研究者からの報告」をご覧ください。